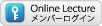ICU入試国際基督教大学入試合格体験記2025(11) たんぽぽさん
<お名前>
たんぽぽ
<プロフィール>
都内の国際バカロレア(IB)校に通っていて、DP生でした。
DP生なのに総合型選抜やIB認定校試験を使わないことは結構レアで、結構心細かったのですが頑張りました。
対策はオンレクのみで予備校は使っていません。
趣味は絵を描くことです。
2.受験形態
一般選抜
3.予想得点
人文社会 = 8-9割
総合教養得点 = 7割
英語リスニング得点 = 9割
英語リーディング得点 = 8-9割
センター得点 = 共通テストは受験していないです。
4.併願校
中央大学 国際情報、国際経営
慶應義塾大学 総合政策、環境情報
5.ICUに入るまでのいきさつ(どうやってICUを知ったか? なぜICUを選んだか ? など)
オープンキャンパスでICUを見に行った時の、のんびりした雰囲気が好きでICUを選びました。
以前から高校生向けのICUのイベントに参加したり、ICUの在校生の方と関わりがあったりと、なにかとご縁は多かったのですが、決め手はICU独特のあの雰囲気だったと思います。
6.ICUに期待するところ
結構いろんなことに興味があるタイプなので、様々な学問を幅広く追及していきたいです。
あと、高校では軽音部に入りたかったのですが、勇気が出ず辞めてしまったので、音楽系のこともなにかできたらいいなあ…と思っています。
7.受験対策
a.願書
<1.ICUを志望した動機または理由を述べてください。あわせて、ICUで何を学びたいか、その理由も含めて述べてください。>
志望動機には「私がICUのリベラルアーツ教育に魅力を感じた理由は、「対話」を軸に知を構築する姿勢にある」みたいなことについて端的に書きました。
何を学びたいか、のところについては、「芸術を通じて人権問題をいかに解決できるか」をテーマに学びを深めたいと考えているということを書きました。
<2.学内外を問わず、技能、諸活動等自分の最も得意とすること、好んで行っていることを述べてください。 >
絵を描くことや美術館巡りが好きなことについて書きました。
a. 人文・社会科学
25年分ほどの人文・社会科学の問題を解き(2015年以前のものは人文科学と社会科学に分かれていたので、量だけで言えば25個以上は解きました)ICUの問題の「癖」みたいなのに慣れることを目的としました。
その際、google documentにそれぞれの年ごとの目立った特徴と、自分がどこで躓いたについて表にして試験直前に見返せるようにしていました。
人文 ・社会科学は年によって割とばらつきがありますが、さすがに20年以上もやれば試験当日にも「なんか見たことあるような形式だなぁ」という気分になれます。
実際私も試験当日は「〇〇年のやつと〇〇年のやつを混ぜたような感じか~」と冷静に対処できたので、気持ち的に落ち着くという意味でも、この世に存在する過去問をできるだけ解くことは有効だと思いました。
精神的な面以外でも、やっぱり過去問をやればやるほど実力がついてきている実感もあったので、たくさん解く!のがいいと思います。
b. 総合教養(ATLAS)
人文 ・社会科学では合格したのですが、残念ながら英語外部試験利用では一次選考不合格となっていたので、総合教養のアドバイスはあまり役に立たないかもしれませんが一応…。
読解の部分は人文 ・社会科学とおんなじ感じですが、講義関連の設問に関しては、これも過去問をとにかく解いて、講義中のどこの部分のメモを取るか・取らないかを取捨選択することが大事なのかなあと思いました。
c. 英語(リスニングを含む)
<リスニング>
英語の部分は帰国子女であるということ、また高校2~3年生の間はDPのEnglish A (英語が第一言語の人向けに開講されるクラス)を履修していたため、こちらもあんまり参考にならないかもですが、一応似た状況にいる人向けに書きます。
まずPart Ⅰ、Ⅱに関しては毎年似たような問題が出るので、こちらも過去問をやりまくって慣れることを重視したほうがいいと思います。
(とはいいつつ、今年度のPart Ⅰでは今まで聞いたこともないような会話が出てきて結構ヒヤヒヤした記憶があります…。私はてっきり例年通り出るだろうと慢心していたので、過去問と違うかもしれないという緊張感は持っておいた方が良かったなと後々思いました。)
Part Ⅲでは結構専門的な語彙が出ることが多いので、わからない単語は後でまとめて暗記することを気を付けました。Readingで出てくる分野とListeningの講義パートは割と重複する部分がある気がしなくもないので、Readingに出てくる専門用語系の語彙も要チェックだと思います。
<リーディング>
Readingも同じく過去問をたくさん解くのがいいと思います。
Reading、Listening共にに二十年分くらいを二週していました。
d.その他受験に関するアドバイス(役立つ参考書、試験中に気をつけること、全般的な勉強法など)
プロフィールのところにも書かせていただいた通り、私は同じクラスの子たちが国内の大学にどんどん内定が決まっていく中、帰国子女選抜・総合型選抜(IB校認定型)にも落ちてしまい(!)、本当に心が折れそうでした。
最近は推薦を多くとる大学もすごく増えてきたので、DPに限らず、総合型に力を入れている系の学校の生徒さんだと私と同じ状況の人もいると思います。
私も割とDP一本でやっていたので、まさか自分が一般で受けることになるなんて思いもせず、本当に心配でたまりませんでしたが、最終的にはHigh Endeavor奨学金をいただけるまでになりました。
受験に限らず、人生全般に言えることですが、失敗した過去があるからと言って未来も同じく失敗するわけではないと思うので、私とおんなじような状況にいる人たちには心の底から頑張ってほしいと思います。
逆に、私が帰国子女選抜・総合型選抜で受からなかった理由は、途中で「私にはどう頑張っても無理だ」と半ばあきらめてしまったことにあるのかな、と今振り返って思うので、今どんな状況にあったとしても、「自分にはどうせ…」と思い込みすぎないことがいいのかなと思います。未来は誰にも分りません。
8. 最後に一言
周りの子たちが受かって、のんきに卒業旅行や卒業式の祭典に向けて準備をしていく姿を片目に勉強するのはつらかったです。
周りと比較せず、と言うのは簡単ですが、実際にそのマインドでいるのはキツいと思います。ただ、ICUの試験自体、「受験」という目的を抜きにしてもすごく読みごたえがあって学びがあるものばかりです。私は周りと比較するのはやめられなかったので、せめて「こういう良い文章が読めなくて残念だったな!」と思うようにしていました。
最初は絶望から始まった私の一般受験ライフでしたが、最終的には一般受験で受けてよかったと思えるようになるくらい心身共に鍛えられました。同じような状況に置かれた人たちの光になれたらいいな、と思います。
あとインスタを見るのはおすすめしません(むなしくなるので)。私は一般受験を覚悟した日くらいから合格発表日(今日)までアプリを削除していました。
ICU Peacebell, High Endeavor共に申し込んで、結果的にHigh Endeavorの方を内定することができました。
オンレクは偏差値などで自分の立ち位置が確認できたのが良かったです。周りで一般受験の子が少なく、自分の位置を相対的に見ることが難しかったため、ここはすごく役に立ちました。
(追加の質問)
・IB校で一般選抜受験はあまり多くないという点で、所属高校では何割ぐらいの方が総合型選抜やIB校入試、推薦等の一般選抜以外で大学に進学するの?
私の通っている高校は、そもそもディプロマ・プログラム(DP: IBのコースの中で高2~3が履修することができるもの)の生徒が毎年10~15人と非常に少なかったため、年度によってかなり生徒の傾向が変わっている印象があります。なので正確な割合は正直に言うとブラックボックスなのですが、個人的な体感でお話しさせていただきます。
今年度の私のケースで言うと、5割程度が海外進学を目指していて、そういう人たちは滑り止めに国内を受験するので、早めに合否が出る総合型やIB校入試しか受けないというのが定石でした。
残りの5割は国内進学を目指すのですが、そういう人たちも割と総合型やIB校入試に力を入れていた印象があります。結構周りのDP生の子でもICUにIB校入試で受かってる子がいました。というのも、DPで学ぶ内容が国内の勉強の範囲とあまりにも差異がありすぎるので、DPと一般入試の両立は非常に厳しく、DP生向けの進路指導の時間でも主に総合型の対策などの話しかなかったです。それでも一般受験をしているクラスメイトもいたのですが、そういう人たちはもうすでにほかのどこかの大学から内定をもらっていて、チャレンジとしてもう少しレベルの高いところを受験する、というケースしかなかったです。なのでまだどこにも受かっていなかった私は必然的にすごく孤独でした笑
・IB校で良かった点と大変だった点は?
良かったこととしては、アカデミックな議論をするための土台を学ぶことができたことと、自分を俯瞰的に見つめる機会が多くあったことがあげられると思います。
IBでは各教科でテストだけでなくミニ論文的なものを課されたり、Extended Essay(課題論文)というミニ卒論みたいなものを書かされました。なので、論文そのものの形式に慣れたり、それぞれの学問における研究がどんな感じで行われるかについて理解の土台が作れたことはよかったです。また、授業内で頻繁にディスカッション・プレゼン・小論文の課題が課されるため、自分の考えを他者と相対化して捉える機会が多かったです。なので、自分なりの「思考の癖」みたいなのを捉えることができ、他者理解も自己理解も深まったなと思います。これは勉強だけじゃなく人生全般について考えるときも役立つスキルになりました。
大変だった点は、とにかく課題の量が多いことと、勉強のリソースが限られていることです。IBの課題は本当に多いうえに良い成績を取ろうと思うと才能も粘り強さもどちらも必要なのでキツかったです。また、これは私が一般受験対策を始めてから痛感したことですが、IBは日本にあまり浸透していないこともあって、リソースが本当にないです。もちろん本屋さんに行ってもIB向けの参考書なんてありませんし、YouTubeで調べても役立つ情報は限られています…。なので、どうやって勉強を進めていったらいいのか闇雲に進めるしかなかったです。なので結構2年間不安いっぱいでしたが、得られることも多かったので、やってよかったなとは思います。
長くなってしまいましたが、現DP生や将来IBをやりたいと考えている人の参考に少しでもなれば幸いです。