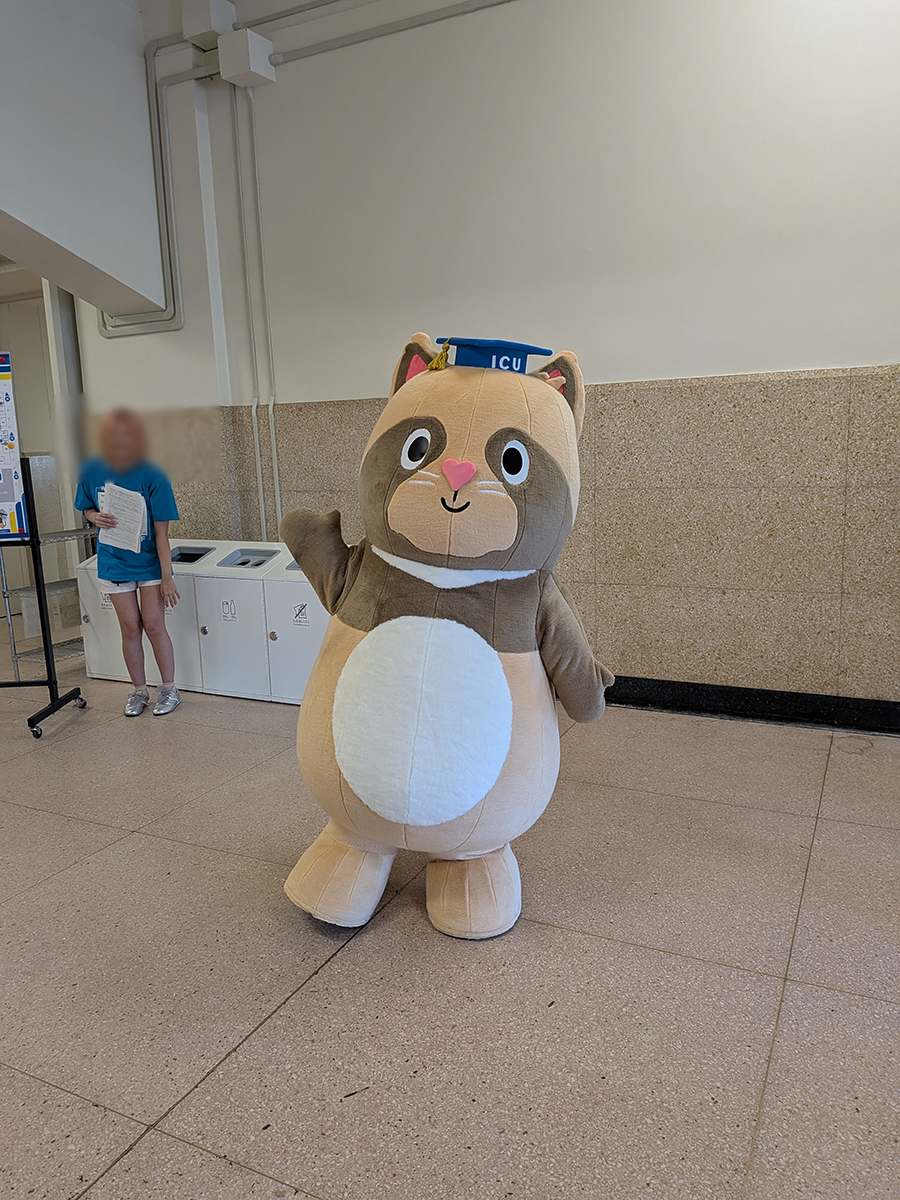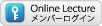ICU総合型選抜2026 入試合格者減の背景――収容定員充足率の上昇、一般選抜への影響は?
2026年度ICU総合型選抜入試結果

2025年11月4日に2026年度ICU総合型選抜の合格発表が行われました。2026年度のICU総合型選抜では、志願者が増加する一方で合格者が減少しました:
| 年度 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 75 | 367 | 117 | 約3.1倍 |
| 2026 | 75 | 406 | 81 | 約5.0倍 |
| 増減 | — | +39(+10.6%) | -36(-30.8%) | +1.9倍 |
志願者が39名(+10.6%)増加した一方で、合格者は36名(-30.8%)減少し、倍率は3.1倍から5.0倍へと上昇しました。ICUの総合型選抜では2023年度以降は100名以上が合格していましたが、4年ぶりに合格者総数が100名を下回る結果になりました。
方式別の募集人員明確化と入試名の変更
2026年度から、総合型選抜の方式別の募集人員が初めて明文化され、同時に入試名に「4月入学専願」という文言が明示されました。
| 方式 | 募集人員 | 志願者 | 合格者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 英語外部試験利用 | 60 | 365 | 74 | 約4.9倍 |
| 理数探究利用 | 5 | 6 | 0 | —(合格者なし) |
| IBDP利用 | 10 | 35 | 7 | 約5.0倍 |
| 合計 | 75 | 406 | 81 | 約5.0倍 |
英語外部試験利用に志願者の約90%が集中し、理数探究利用は合格者ゼロという厳しい結果になりました。
ICUの総合型選抜の合格者数が減少した要因
収容定員充足率の上昇
収容定員充足率とは、大学の収容定員(全学年の定員合計)に対する実際の在籍学生数の割合です。ICUの収容定員充足率は以下のように推移しています:
| 年度 | 学生数合計 | 収容定員 | 収容定員充足率 |
|---|---|---|---|
| 2024年10月 | 2,773 | 2,480 | 111.8% |
| 2025年10月 | 2,834 | 2,480 | 114.3% |
| 増減 | +61 | — | +2.5ポイント |
2025年10月時点で、ICUの収容定員充足率は114.3%に達しました。前年度の111.8%から2.5ポイント上昇しています。
文部科学省は経常費補助金の交付判定を毎年5月1日現在の在籍者数を基準に行い、収容定員超過が大幅な場合は交付停止・減額という指導を行っています。不交付基準は大学規模により異なります:
- 大規模大学(学部収容定員8,000人以上):1.10(110%)
- 中規模大学:1.20(120%)
- 小規模大学:1.30(130%)
ICUは小規模大学に分類されるため、不交付基準は1.30(130%)です。現在114.3%は基準までに15.7ポイント離れているように見えますが、ICU特有の構造があり、充足率には余裕を持たせる必要があります。
在籍管理を複雑にする要因
ICUが114.3%という充足率で合格者を抑制する背景には、単なる数字の上昇だけでなく、在籍管理上の複雑な構造があると考えられます:
中長期留学による在籍変動: ICUはリベラルアーツ教育と国際性を標榜しており、学部生の中長期留学(1年派遣・交換留学等)の比率が相対的に高くなっています。在籍管理上は、留学中の学生も在籍者としてカウントされるため、留学・復学の時間的ずれが充足率判定時点の在籍者数に反映されやすい構造です。
厳格な進級要件による留年・在籍延伸: ICUは厳格な成績運用と課題負荷の高いリベラルアーツ・カリキュラムを特徴としており、進級要件のハードルが相対的に高く設定されています。この結果、一定程度の留年・在籍延伸が発生しやすく、特に4年生の在籍が厚くなりやすい傾向があります。
複数学年合算による高止まり効果: 補助金判定は5月1日現在のすべての在籍学年を合算して判定されます。ICUのように中長期留学者が相対的に多く、かつ最終学年に留年・再履修による上級生が厚く存在する大学では、充足率が高止まりしやすい構造になっています。
専願制による高歩留率: 2026年度から入試名に「4月入学専願」が明示されたように、ICUの総合型選抜は専願制であり、合格者のほぼ全員が入学する高歩留率(入学率)を特徴としています。推薦入試に近い性質を持つこの制度では、合格者数がほぼそのまま入学定員に直結します。
2025年度の入学者数の増加がもたらした定員充足率の上昇
以下の表はICUの2022年度から2025年度の入学者数を示しています:
| 年度 | 入学者数(本科) | 転入本科生 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 670 | 11 | 681 |
| 2023 | 615 | 18 | 633 |
| 2024 | 613 | 19 | 632 |
| 2025 | 726 | 14 | 740 |
2025年度のICU入学者は740名でした。前年度(632名)から108名(+17.1%)の増加です。この入学者の増加が充足率の上昇をもたらしました。
ICUの収容定員は約2,500名で、入学者数の変動が充足率に相対的に大きく反映されやすいという特徴があります。100人規模の増減でも、充足率が数ポイント動く場合があります。
ICU入試の構造的特徴:調整手段の制約
ここで重要な要素が、補欠合格制度の有無です。多くの私立大学は補欠合格制度を採用しており、入学辞退者が出た場合は補欠から繰り上げ合格を出すことで、入学定員を微調整できます。一方、ICUは補欠合格制度を採用していません。
さらに、ICUは単一学部制であるため、他の総合大学のような「学部間での定員相殺」も機能しません。つまり、一度合格者を決定したら、その後の調整余地がほぼないという特殊な構造です。
この制約条件下では、あらかじめ合格者数に余裕を持たせて、翌年度以降の充足率を抑える戦略が必須になります。2026年度の総合型選抜で合格者数が前年度より抑制された背景には、このような構造的要因があったものと推測されます。
他大学との比較
同じ「充足率上昇」でも、大学の構造により対応策は異なります:
| 大学 | 規模 | 充足率 | 不交付基準 | 基準までのポイント | 補欠合格 | 学部構成 | 対応余地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICU | 小規模 | 114.3% | 1.30(130%) | 15.7ポイント | 無し | 単一学部 | 限定的 |
| 上智 | 大規模 | 109.5% | 1.10(110%) | 0.5ポイント | 有り | 複数学部 | 学部間相殺 + 補欠制度 |
| 津田塾 | 小規模 | 119.3% | 1.30(130%) | 10.7ポイント | 有り | 複数学科 | 学科間相殺 + 補欠制度 |
上智大学は学部収容定員11,340名、学部在籍12,419名(2025年5月1日現在)で、学部充足率は109.5%です。大規模大学の不交付基準は1.10(110%)であり、上智の109.5%は不交付基準にわずか0.5ポイントしかないという際どい状況です。ただし、複数学部制による学部間相殺と補欠合格制度により、調整が可能です。大規模校のスケールメリットもあり、100人程度の変動でも吸収しやすいとは言えます。
津田塾大学は学部収容定員2,760名、学部在籍3,294名、(2025年5月1日現在)で、全体充足率は119.3%に達しています。同じ小規模大学でありながらICUより充足率が高い水準ですが、学科別では英語英文学科が113.7%、情報科学科が116.7%と比較的低く、学科間で相殺が機能しています。さらに補欠合格制度も採用しており、二重の調整手段を持ちます。
ICUはこうした調整手段を持たないため、専願制で確実に入学する総合型選抜の合格者を事前に抑制することが、翌年度以降の充足率管理の重要な手段となったと考えられます。
充足率管理と教育方針の関係
収容定員充足率は1年生から4年生までの全在籍者を合算して計算されるため、留年者が増えると在籍者総数が増え、充足率を押し上げてしまいます。例えば、2025年現在の上智大学のように基準まで0.5ポイントという非常に差し迫った状況では、大多数の学生に4年間でスムーズに卒業してもらうことが大前提となります。つまり、留年を増やす方向(成績評価の厳格化、進級要件の引き上げなど)には向かいにくく、むしろ卒業を円滑化する圧力が働く可能性が高くなると考えられます。
一方、ICUは充足率114.3%で小規模大学の基準1.30まで15.7ポイントの余裕がありながらもさらに充足率を低く抑制しようとしているように見受けられます。
厳格なカリキュラムの維持: ICUは1年生から週に約10コマ(Streamによる)ものELA(English for Liberal Arts)の授業が課されるカリキュラムを特徴としています。課題負荷が高く、出席等の要件も厳格であるため、一定程度の留年・在籍延伸が発生しやすい構造です。しかし、充足率に余裕があることで、こうした厳格な教育を維持しても、充足率管理上のリスクを吸収できていると考えられます。
積極的な留学推奨とその影響: さらにICUは海外留学を積極的に推奨しています。交換留学は在学しながら海外で単位を履修する形のため、留学中の学生も在籍者としてカウントされます。加えて、就活や進学のタイミングから、留学により半年から1年程度卒業が遅れるケースも一定数発生します。留学に行く学生が増えれば増えるほど、在籍延伸により充足率は上昇圧力を受けるため、ICUは充足率に余裕を持たせておく必要があると言えます。
まとめ
2026年度ICU総合型選抜の合格者減少は、以下の複合的要因によるものです:
- 2025年度入学者の増加(+108名)により収容定員充足率が上昇
- 補欠合格制度が無く、単一学部制で学部間相殺が無いこと
- 総合型選抜が専願制であることによる高い入学率(歩留率)
- 留学・留年による在籍変動の構造的要因
これらの要因に加えて、2026年度から総合型選抜の3区分の定員が明確化され、より区分ごとに受験者のクオリティから合格者を出すようになったという見方もできます。
2026年度一般選抜への影響
すでに充足率のバランスを取る対応を年内入試で行ったことで、一般選抜は昨年度より余裕がある状況という見方もできます。確かに昨年度の入学者の増加で充足率は上昇しましたが、それでも他の小規模大学と比較して高い水準ではないことを踏まえると、一般選抜の合格者は例年通りになるのではないかと予想します。特に一般選抜では昨年度から複数方式の併願方法が拡充され、併願を活用してICUに合格する受験生も増えていますので、複数方式の活用が一般選抜の対策では重要になりそうです。